🍅 はじめに
「薬とサプリ、一緒に飲んでも大丈夫?」
「サプリは自然の成分だから安心じゃないの?」
健康意識が高まる中、薬とサプリを併用する人が増えています。
でも、サプリも体に作用する“成分”を含むもの。
薬との飲み合わせによっては、思わぬ影響が出ることがあります。
この記事では、薬剤師トマトラが
公的機関のデータをもとに「サプリと薬の安全な付き合い方」を解説します🍅
💊 サプリと薬の違いを知ろう
| 比較項目 | 医薬品 | サプリメント(健康食品) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 病気の治療・予防 | 栄養補助・健康維持 |
| 成分量 | 有効成分が明確・一定 | メーカーによってばらつきあり |
| 効果の証明 | 臨床試験などで有効性を確認 | 基本的に「期待」レベル |
| 承認制度 | 国が審査・承認 | 食品として販売可(表示基準のみ) |

サプリは“薬の代わり”ではなく、“補うもの”。
薬と同じ効果を狙って重ねるのは、思わぬ副作用につながることがあります。
⚠️ 一緒に飲むと注意が必要な組み合わせの一例
| サプリ | 注意が必要な薬 | 主な理由 |
|---|---|---|
| セントジョーンズワート(SJW) | 抗うつ薬、睡眠薬、ピルなど | 薬の代謝を早め、効果が弱まる(PMDA報告) |
| ビタミンKを多く含む青汁など | ワルファリン(血液をサラサラにする薬) | 血液を固める作用で薬の効果が減る |
| カルシウム・マグネシウム | 抗菌薬(ニューキノロン系・テトラサイクリン系) | 錯体を作り吸収が妨げられる |
| 鉄サプリ | 甲状腺ホルモン薬(チラーヂン®など) | 鉄が薬の吸収を阻害する |
| EPA・DHA(魚油) | 抗血小板薬・抗凝固薬 | 出血傾向のリスクが上がる可能性 |

💡 **PMDA(医薬品医療機器総合機構)による注意喚起(2022年)**では、「健康食品・サプリメントと医薬品の併用で効果が変化・副作用が出た事例」が報告されています。
特にハーブ系やミネラル系のサプリは、医薬品と同じ代謝経路を通ることがあり、
**“自然のものでも油断は禁物”**とされています。
🧠 安全に続けるための3つのコツ
① 飲む時間をずらす(2時間以上)
吸収のタイミングをずらすだけで、相互作用のリスクを減らせます。
② サプリは“おまけ”と考える
薬の代わりではなく、あくまで健康維持の補助。
薬を飲んでいる場合は、主治医や薬剤師にサプリの内容を伝えましょう。
③ 「健康食品データベース」で確認する
国立健康・栄養研究所が公開する「健康食品データベース」では、
各成分の安全性や医薬品との相互作用の報告を確認できます。

💡 国立健康・栄養研究所の調査では、健康食品と医薬品を併用している人のうち、医療者に相談している人は少数との結果がでています。
サプリを始める前に、「薬剤師にちょっと聞く」習慣をつけよう。
🩺 サプリも「お薬手帳」に書いてOK!
日本薬剤師会の公式ページでは、
「サプリメントや健康食品の使用もお薬手帳に記録しておく」ことが推奨されています。

医薬品だけでなく、サプリメント・健康食品も“体に影響を与えるもの”。
飲み合わせ確認や副作用チェックのために、薬剤師に共有することが大切です。
🍅 まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ✅ サプリと薬は成分が重なると作用に影響 | 特にハーブ・ミネラル系は注意 |
| ✅ 飲む時間をずらす・相談する | トラブル予防に最も効果的 |
| ✅ データベースや薬剤師を活用 | 自分だけで判断しないのが安全 |

サプリも「体に効くもの」だからこそ、
“薬と一緒に飲んで大丈夫か”を確認するのが安心への第一歩。
🩺 参考文献
- 医薬品医療機器総合機構(PMDA)「健康食品と医薬品の相互作用」
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「健康食品の安全性」
- 国立健康・栄養研究所「健康食品データベース」
- 日本薬剤師会「サプリメントと薬の飲み合わせ」
🍅 トマトラからひとこと

「サプリも薬も、“体を良くしたい”という想いは同じ」。
でも、安全に続けるには一緒に飲むタイミングを知ることが大切。
気になるときは、薬剤師トマトラに気軽に相談してね🍅✨


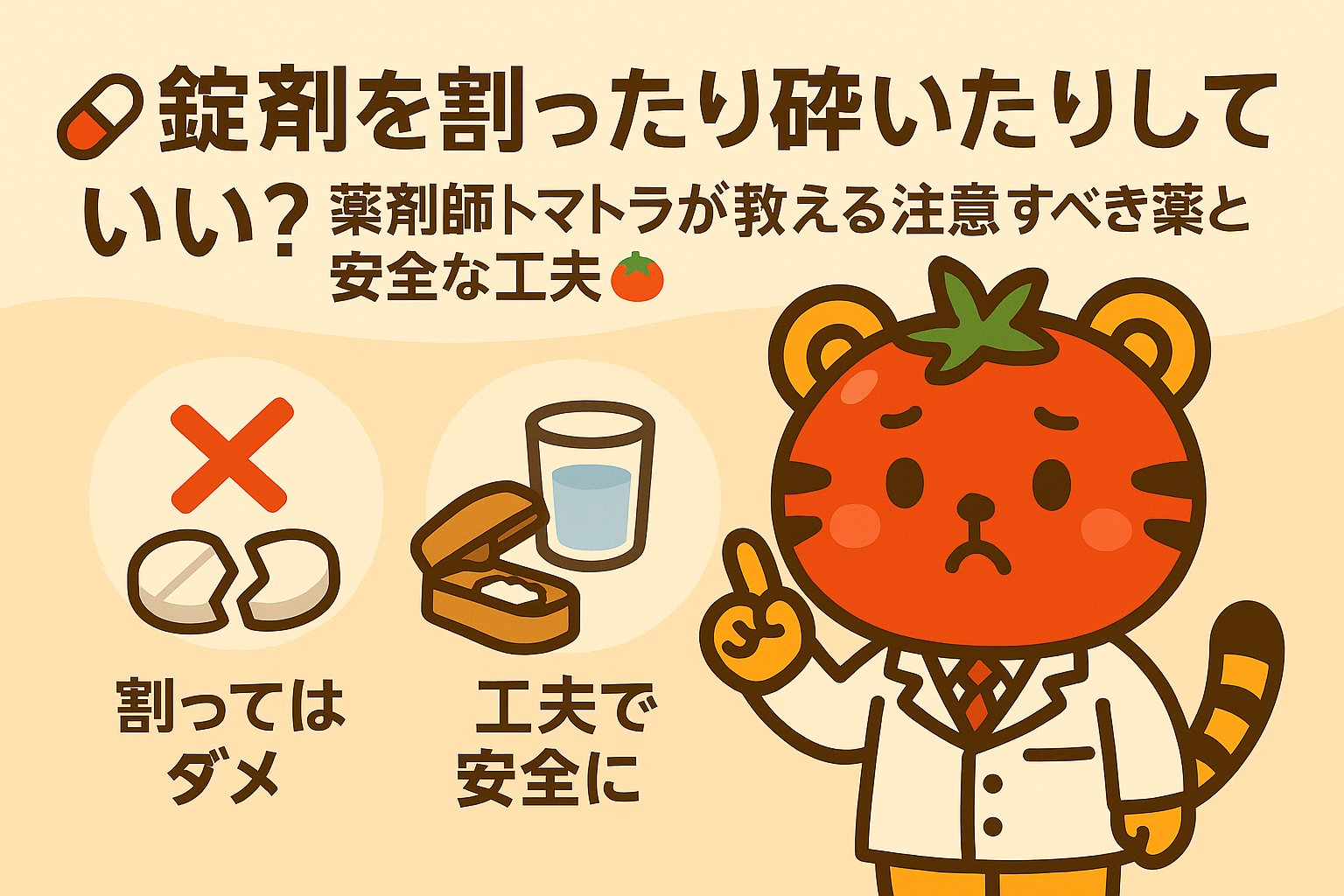
コメント